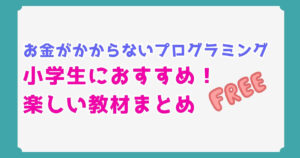- 小学生でもプログラミング資格って取れるの?
- 種類が多すぎて、うちの子にどれが合うのかわからない…
- そもそも資格なんて、本当に将来の役に立つのかな?
そんなふうに、お子さんのプログラミング資格について、たくさんの情報の中で迷子になっていませんか?
小学生の子どもを持つ私も、まさに今、同じことで頭を悩ませています。

「この資格は本当に信頼できるの?」「費用対効果はどうなの?」という現実的な疑問が、次から次へと浮かんできますよね。
わが家では子どもがプログラミングを習い始めてしばらく経つので、これから資格に挑戦しようと考えています!



実際に私は、国家資格の「ITパスポート」だけでなく、「基本情報技術者」「応用情報技術者」も取得しています。
だからこそ、実際にプログラミングを習わせている子を持つ親として、そしてこれから資格挑戦を考える当事者として、「小学生のプログラミング資格って、実際のところどうなの?」という疑問に、徹底的にリサーチした情報をもとに、正直にお答えします。
この記事では、私がまとめた「ここが知りたかった!」と感じたポイントを中心に、わかりやすく解説します。
- 小学生でも挑戦できる資格には、どんな種類があるのか
- 資格取得にかかる、リアルな費用と時間の目安
- わが子にぴったりの資格を見つけるためのチェックポイント
- もし挑戦するなら、どんな勉強法や親のサポートが必要なのか
- そして一番気になる、資格の本当の将来性



この記事を読み終える頃には、プログラミング資格に対するモヤモヤとした不安が晴れるでしょう。
はじめに|プログラミング資格が気になり始めた保護者の方へ


「プログラミングを習っているけれど、どのくらい力がついたのかな?」 「周りの子たちは、どんなことをしているんだろう?」
学習を進める中で、ふとそんな風に思うこと、ありますよね。 何か目標があれば、もっと頑張れるかもしれない。でも、どんな資格があって、何がどう違うのか、判断が難しいのも本音です。
そんな中で注目されているのが、小学生向けのプログラミング資格。 大切なのは、やみくもに受けさせるのではなく、その子の性格や関心に合っているかどうか。
この記事では、現在選べる代表的な資格を、目的別に分かりやすく整理しました。「何を選べばいいか」が見えてくるだけで、迷いはぐっと減っていきます。
【種類】小学生が挑戦できるプログラミング資格一覧|目的別に徹底比較


プログラミング資格といっても、内容はさまざま。 まずは、どんな資格があるのか、全体像を見てみましょう。資格選びに迷ったら、「どんな子に向いているか」を出発点にすると、選びやすくなりますよ。
| 資格名 | 主な対象 | レベル | 試験形式 | 学べること | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア・プログラミング検定 | 小学生~ | 4級~1級 | 作品制作 | Scratchでのゲーム作り | ゲーム作りが好きで、楽しみながら挑戦したい |
| プログラミング能力検定(プロ検) | 小学生~ | 6級~1級 | テスト形式 | ビジュアル言語、テキスト言語 | 将来を見据えて、段階的に力を試したい |
| 日商プログラミング検定 | 小学生~ | 初級~上級相当 | テスト形式 | 基本的なPC知識、プログラミング | PCの基礎からしっかり固めたい |
| ITパスポート | 社会人全般 (※高校生以上推奨) | 国家資格 | テスト形式 | ITに関する総合的な知識 | 高校生以上で、本格的な国家資格に挑戦したい |
① ゲーム好きの子ども向け|ジュニア・プログラミング検定
「テスト形式はちょっと苦手かも…」 そんな場合に、まず検討したいのがこの検定です。
Scratch(スクラッチ)というツールで、オリジナルのゲームや物語を作るのが試験内容。 決められた正解を答えるのではなく、自分のアイデアを形にする力が問われます。
「こんな動きをさせたい」「こんなキャラクターを登場させたい」 そんな自由な発想や、創造する力が評価されるのが、一番のポイント。



まさに、楽しみながら実力を試せる検定です。
② 将来を見据えたい子ども向け|プログラミング能力検定(プロ検)
「今の実力を、客観的に知りたい」 「大学入試なども見据えて、段階的にステップアップしたい」 そんな考えに、しっかり応えてくれるのが、この「プロ検」です。
レベルは6級から1級まで。 最初はブロックを組み合わせる簡単なものから始まり、級が上がるにつれて、大人も使う本格的な文字のコード(テキストコーディング)へと進んでいきます。



大学入試で評価されることもあるなど、将来に繋がる可能性も。
今の立ち位置を確認しながら、着実に力を伸ばしていきたい、という場合に良い目標になります。
③ PCの基礎から固めたい子ども向け|日商プログラミング検定
「プログラミングだけでなく、パソコンの基本的な知識も身につけてほしい」 そんな思いがあるなら、商工会議所が実施しているこの検定も、視野に入れたいところ。
この検定の特徴は、プログラミングの考え方に加えて、ファイル操作や文字入力といった、パソコンの基本的な知識も問われる点。
これからの時代に欠かせない、ITの基礎体力をバランスよく育てることができます。



全国の商工会議所で受験できる、という安心感もありますね。
④ 国家資格の第一歩として|ITパスポート(高校生以上推奨)
最後に、少しレベルは上がりますが、知っておきたいのがこの「ITパスポート」。 これは、国が認める「国家資格」の一つです。
プログラミングの技術だけでなく、セキュリティやネットワーク、経営のことまで、ITに関する幅広い知識が問われます。
小学生が今すぐ受けるには少し難しいですが、「将来は、こんな資格もあるんだよ」と、遠い目標として知っておくのも良いかもしれません。



プログラミング学習の、一つのゴールになる資格です。
【費用・時間】資格取得にかかる費用と学習時間の目安


「資格に挑戦するとして、費用や時間はどのくらい必要なんだろう?」 そんな現実的な疑問について、見ていきましょう。
費用の内訳をシミュレーション(受験料・教材費・スクール代)
資格取得には、思った以上に細かな出費が重なることも。 受験料だけではなく、学習方法によって教材費や教室代も必要になります。
| 資格名 | 受験料の目安(税込) | 対策方法の例 |
|---|---|---|
| ジュニア・プログラミング検定 | 2,800円 ~ | 市販のテキスト、対策講座のある教室 |
| プログラミング能力検定(プロ検) | 3,300円 ~ | 公式サイトの教材、認定教室 |
| 日商プログラミング検定 | 5,500円 ~ | 公式の学習アプリ、テキスト |
| ITパスポート | 7,500円 | 市販のテキスト、学習サイト |
※級やレベルによって受験料は異なります。
受験そのものよりも、「どう学ぶか」で総額が大きく変わります。 市販のテキストだけで学ぶなら数千円で済みますが、教室に通う場合は月々の支払いも。



学び方を選ぶ前に、全体像を把握しておくと安心ですね。
合格までに必要な学習時間はどれくらい?
資格のレベルや、これまでの学習経験によって必要な時間は異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。
| 資格名 | 合格までの学習時間(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| ジュニア・プログラミング検定 | 15~30時間 | Scratch経験があると短縮可能 |
| プログラミング能力検定(プロ検) | 20~40時間 | 高学年向けはより長くなる傾向 |
| 日商プログラミング検定 | 30~50時間 | PC操作に慣れていないと時間増 |
| ITパスポート | 100~150時間 | 高校生や初学者の場合 |
取り組む前に目安を知っておくことで、無理のないスケジュールが立てやすくなります。



資格によって内容の重さが異なるため、対象年齢やスキルに合わせて選ぶことが大切ですよ。
【選び方】後悔しないための3つのチェックポイント


たくさんの選択肢の中から、何を選べばいいのか。 最後に、後悔しないための3つのチェックポイントをお伝えします。
ポイント①:子ども自身が「楽しい」と感じるか
資格を取ること自体が目的になると、途中で気持ちが離れてしまうことも。 何より大切なのは、「自分からやりたくなるかどうか」。 プログラミングは、本来おもしろいもの。興味を持って続けられる内容か、まず確認してあげたいですね。
ポイント②:日々の暮らしのペースや予算に合っているか
送迎の有無や、通塾の頻度。さらに月謝や教材費。 時間と費用のバランスは、始めてから後悔しやすいポイントです。 教室に通うのか、市販の本で自宅学習するのか。その選び方ひとつで、日々の負担が大きく変わります。
ポイント③:資格取得を「ゴール」ではなく「通過点」にできるか
合格して終わり、ではなく、その後の学びにどうつながるかが本当のポイント。 検定を通して、自分に何ができるようになったか。 それを感じられるような学び方を意識することで、「資格を取ってよかった」という実感につながります。
実際に資格取得を目指すなら、このプログラミング教室がおすすめです。理由も書いているので、ぜひチェックしてください。


【勉強法】合格を目指すための学習方法と、親のサポート


「よし、挑戦してみよう!」 そう決めたら、次に考えるのは「どうやって勉強するか」。 教室に通う方法と、自宅で学ぶ方法。それぞれに向き不向きがあるため、特徴とサポートのしかたを整理しておきましょう。
選択肢①:プログラミング教室で学ぶ
教室に通うメリットと注意点
専門の先生に指導してもらえる安心感。 分からないところを、その場で解決できるのが教室の強みです。つまずきやすい部分を丁寧に見てもらえる点は、大きな利点。
ただし、通いやすさと費用には注意が必要。 送迎の負担や月謝の継続的な支払いをふまえて、無理のない通い方を考えることが大切です。
失敗しない教室選びのコツ
教室選びで後悔しないためには、いくつかのポイントがあります。 一番大切なのは、やはり体験授業での様子。 先生との相性や教室の雰囲気は、実際に行ってみないと分かりません。
より詳しい教室選びのポイントは、こちらの記事で解説しています。


選択肢②:家庭学習で学ぶ
家庭学習のメリットと乗り越えたい壁
費用をおさえて、自由なペースで進められる。 市販のテキストやオンライン教材を使えば、好きな時間に学べます。忙しい日々の中でも、少しずつ取り組めるのが利点です。
一方で、継続の難しさも。 集中力が続かない、つまずいて止まってしまう、教材選びが難しい。 こうした悩みが出てくることもあります。
評判の良い市販テキスト・オンライン教材【リサーチまとめ】
家庭学習を進める上で、心強い味方になってくれる教材。 資格ごとにおすすめのものを、いくつか調べてみました。
以下のような表になります。
| 資格名 | おすすめの教材例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ジュニア・プログラミング検定 | 「できるキッズ スクラッチでゲームをつくろう!」などの書籍 | 分かりやすいイラストで、楽しく学べる。 |
| プログラミング能力検定 | 公式サイトのサンプル問題、レベルチェック | まずは無料で、今の実力を試せる。 |
| 日商プログラミング検定 | 公式の学習アプリ「アルゴロジック」 | ゲーム感覚で、プログラミングの考え方に触れられる。 |
| ITパスポート | 「いちばんやさしいITパスポート」などの書籍、ITパスポート試験ドットコム(過去問道場) | イラストが多く分かりやすい書籍、無料で過去問に挑戦できるサイト。 |
家庭学習での親の関わり方【わが家の検討プラン】
「プログラミングなんて、私には分からないし…」 そう思う方も、多いかもしれません。でも、専門的な知識はなくても、できることはたくさんあります。
大切なのは、「教える」のではなく、「見守る」姿勢。 「今日はどこまで進んだ?」「すごいね、こんなことができるようになったんだ!」 そんな風に、進み具合を確認するだけでも励みになります。
そして、つまずいた時には、すぐに答えを教えるのではなく、「どうしたらいいと思う?」と一緒に考える。 その問いかけが、きっと本人の「自分で解決する力」を育ててくれるはずです。
【将来性】取得した資格は本当に役立つ?中学受験やその先への影響
「この資格、取って意味があるのかな?」 「子どもの将来に、どう繋がっていくんだろう?」 プログラミング資格は、ただの認定書以上の価値があります。将来に向けてどんな意味を持つのか、見ていきましょう。
中学入試でアピール材料になる可能性は?
最近、中学入試でもプログラミングの経験を評価する動きが、少しずつ出てきています。
たとえば、聖徳学園中学校(東京)の「プログラミング入試」や、駒込中学校(東京)の「プログラミング入試」のように、プログラミングの実技そのものを取り入れる学校も。
また、「ジュニア・プログラミング検定」の合格を、入試で優遇する学校も実際にあります。こちらがご希望の内容を表にまとめたものです。
| 学校名 | 優遇の例 |
|---|---|
| 相模女子大学中学部(神奈川) | プログラミング入試で合格判定を考慮 |
| 八王子実践中学校(東京) | プログラミング入試の実技試験を免除 |
| 浜松開誠館中学校(静岡) | 入試選抜結果に加点 |
資格が直接、合否を決めるわけではありません。
ですが、それは努力の証明として、面接や志望理由書で有効なアピール材料になります。 「目標に向かって、継続的に取り組む力がある」という姿勢を示す、一つの大切な材料になると思います!
大学入学共通テスト「情報」への土台作り
これは、とても大きなポイントです。 2025年度から、大学入学共通テストに「情報」という科目が加わりました。
大学入試センターが公表したサンプル問題では、「比例代表選挙の当選者を決める手順(ドント方式)をプログラムで表現する」といった、まさにプログラミング的思考を問う問題が出題されています。
資格の勉強で学ぶ論理的な思考やプログラミングの基本は、「情報」の試験範囲と重なる部分が多いのが特徴です。 難しい言葉を知らなくても、「あのゲームでやったことだ!」と感覚的に理解できる。



先に取り組んでおくことで、共通テストに向けた大きなアドバンテージになります。
資格の先にある、本当に“将来に役立つ”力とは
資格取得は、終着点ではなくスタート。 その過程で身につく、問題解決能力、論理的思考、そして創造する力。 これらは、社会に出てからの大きな武器になります。
プログラミングを学ぶことで得られる、より詳しいメリットについては、こちらの記事にまとめました。


小学生のプログラミング資格に関するよくある質問(Q&A)


プログラミング資格の挑戦を具体的に考え始めると出てくる、細かな疑問や不安についてQ&A形式でお答えします。
- 何年生から挑戦するのがおすすめですか?
-
小学3~4年生から挑戦を始めることが多いようです。まずはScratchなど、ブロックを組み合わせる簡単なものから始め、パソコン操作に慣れてきたタイミングで、一番やさしい級から検討するのが良いでしょう。
- パソコンはどの程度のスペックが必要ですか?
-
問題ありません。ほとんどの受講者が、プログラミング未経験からのスタートです。
初心者向けのコースでは、マウス操作が中心の教材から始めるなど、誰もがつまずくことなく学べるよう配慮されています。プログラミングの経験がなくても、安心して始められます。
- もし不合格だったら、子どもの自信に影響しませんか?
-
大切なのは、結果よりも挑戦した過程を認めてあげることではないでしょうか。「ここまで頑張ったのがすごいね」「次はどうしたらクリアできるか、一緒に考えてみようか」と声をかけることで、失敗も次への学びにつなげましょう。
- どの資格から始めるのが一番良いですか?
-
まずは、作品作りが中心の「ジュニア・プログラミング検定」から挑戦するのがおすすめです。テスト形式ではないため、楽しみながら「合格」という成功体験を積みやすく、次への意欲につながりやすいでしょう。
- 資格の勉強は、学校の勉強の妨げになりませんか?
-
プログラミングで学ぶ「論理的に考える力」は、算数の文章問題や国語の読解にも役立つと感じています。
- 資格に有効期限はありますか?
-
小学生向けのプログラミング資格には、基本的に有効期限はありません。一度取得すれば、その時点でのスキルを証明するものとして、ずっと活用できます。
まとめ|プログラミング資格は、子どもの可能性を広げる一つの選択肢
この記事では、「どんなプログラミング資格があるの?」という疑問から始まり、その種類や選び方、勉強法、そして将来性まで、幅広くお伝えしてきました。
- 資格には種類があり、その子の性格や目的に合わせて選ぶことが大切。
- 中学受験や、新しい大学入学共通テスト「情報」にも繋がる可能性がある。
- 資格取得はゴールではなく、論理的思考力や問題解決能力を育む「通過点」。
- 勉強法は教室と家庭学習があり、それぞれにメリット・注意点がある。
- 何より大切なのは、本人が「楽しい」と感じながら、無理なく続けられること。
プログラミング学習は、これからの時代を生きる子どもたちにとって、大きな力となる可能性を秘めています。論理的に考える力や創造力、問題を解決する力は、将来どんな道に進むとしても役立つ大切なスキルです。
「うちの子には難しそう…」「本当に意味があるのかな…」と迷う前に、まずはその子が「楽しい!」と感じられるかどうかを大切に、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。