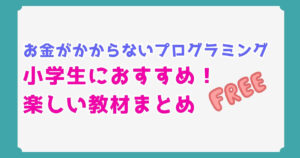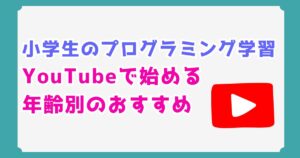- プログラミングが必修化って言われても、うちの子ついていけるの…?
- パソコンが苦手な親に、何ができるのかわからない…
- 結局、何から準備すればいいのか、さっぱり見当がつかない…
そんな悩みをお持ちではありませんか?

この記事では、プログラミング必修化の本当のねらいと、各家庭に合った具体的な準備の方法をお伝えします。
「子どもの将来のために」と必修化について調べ始めても、情報が多すぎて「何が本当なの?」「結局、うちはどうすればいいの?」と混乱してしまいますよね。
そこでこの記事では、ネットの情報だけでは分からない、実際にわが家で試行錯誤してきたからこそ語れる「本音」と「事実」だけをお伝えします!
私は、現在小学3年生の子どもを持つ保護者の一人です。必修化が始まる前から色々と情報を集め、実際に子どもをプログラミング教室に通わせています。その実体験をもとに、具体的でわかりやすい情報をお届けします。
この記事では、わが家のリアルな体験談(成功も失敗も!)をもとに、
- プログラミング必修化で「何を学ぶのか」
- わが家に合った「具体的な準備」
- 小中高の「授業内容」
これらの中から、私が「これだけは知っておいてほしい!」と心から思う情報だけを、わかりやすく具体的にお話しします。
この記事を読み終える頃には、「何をすればいいの…」という漠然とした不安が、「うちの子に合ったやり方で、応援してあげよう!」という前向きな気持ちに変わっているはずです!


なんで今さら小学生に?プログラミング教育が必修になった本当の理由


まずは、「そもそも、なぜ今プログラミングなの?」という根本的な理由に触れておきたいと思います。
- 未来を生き抜く「考える力」を育むため
- 「正解がひとつじゃない」問題に取り組む練習
- コンピュータを怖がらずに使いこなすため
「将来なくなる仕事がある」って本当?親として知っておきたい現実と備え
結論として、プログラミング教育は、変化の激しい未来を生き抜くための「考える力」を養うために必修化されました。
「この子が大人になるころ、今と同じ仕事は残っているのだろうか」未来が見えにくい時代、そんな不安を感じたことがある方も少なくないはずです。AIやロボットの技術が進み、これまで人の手で行われていた作業は、どんどん機械に置き換わっていくと言われています。
でも、だからこそ今、求められているのは「何をすればいいか」を指示されて動く力よりも、「目的をどう達成するか」を自分で考える力。



プログラミング教育は、この“考える力”を育てることが大きな目的です。
将来、どんな職業についても、自分の頭で状況を判断し、工夫しながら前に進める人。そんな人を育てるための、時代に合った学びなのです。
「正解がひとつじゃない時代」に必要な力を育てるための授業
プログラミングには、ひとつの決まった「正解」がありません。それが、これからの時代に必要な力を育む上でとても重要です。
今までは、「正しい答えを、できるだけ早く出す」ことが勉強のゴールでした。でもこれからの社会では、答えがひとつに決まらない課題が増えていきます。
プログラミングの授業では、以下のサイクルをくり返します。
- やってみる: 「こうしたらどうなるかな?」
- 失敗する: 「あれ、うまく動かないぞ」
- 考える: 「どこが違うんだろう?」
- やり直す: 「じゃあ、こうしてみよう!」
まさに、試行錯誤の連続。ここで身につくのは、知識ではなく、「試して考える」という姿勢です。



失敗を重ねてたどりついた「自分だけの正解」を見つける経験が、答えのない問題にも前向きに挑戦できる、粘り強い心を育むのです。
「中身がわかれば、もう怖くない」コンピュータを使いこなす子を育てる第一歩
プログラミング教育は、子どもたちがコンピュータを「理解できる道具」として使いこなせるようになるための第一歩です。
子どもたちの身のまわりには、すでにさまざまなデジタル機器があふれています。でも、その仕組みまで理解している子は、決して多くありません。
プログラミングの授業では、自動ドアや炊飯器など、身近なものが「なぜ動くのか」という“中のしくみ”を体験を通して学んでいきます。「自分で命令を組み立てて動かす」この体験は、コンピュータに対する見方を変えてくれます。
- 学ぶ前: なんだかよくわからない「魔法の便利な箱」
- 学んだ後: 自分で命令して動かせる「理解できる道具」



わからないから怖い。知れば使える。その小さな一歩を、小学校の教室から始めているのです。
【学年別】プログラミングの授業って、結局なにをやるの?


「プログラミング」と聞くと、なんだか難しそうなイメージがあるかもしれませんね。でも、学年ごとに、発達段階に合わせた「楽しい!」と思える工夫がたくさんあるんです。
まずは、小・中・高でそれぞれ「何を学ぶのか」を見ていきましょう。
- 小学校:遊びの延長で、成績はつかない
- 中学校:より実践的に、問題解決に挑戦
- 高校:大学入試にも関わるが、問われるのは「考える力」
【小学校編】算数や理科の中で“自然に学ぶ”プログラミング体験
結論から言うと、小学校では「プログラミング」という新しい教科は増えません。
算数で図形を描いたり、理科で電気の働きを学んだり、そういった今ある授業の中で、道具としてプログラミングに触れるのが基本です。
たとえば、算数の授業で正多角形を描くとき。今までは分度器と定規を使っていましたが、そこに「Scratch(スクラッチ)」のような、ブロックを組み合わせるだけの簡単なツールが登場します。ゲーム感覚でキャラクターを動かしながら、「こうすれば、こう動くんだ!」という発見と、論理的に考える楽しさを体験します。
このように、あくまで体験が中心。



成績がつくわけではないので、まずは「楽しい!」と感じることが一番の目標です。
【中学校編】社会とつながる学びへステップアップ!現実の問題をテーマに
中学校では、技術・家庭科の「技術」の授業で、より本格的にプログラミングを学びます。
小学校で育んだ「考える力」を使い、身の回りの課題を解決するという、より実践的なテーマに挑戦するのが特徴です。
たとえば、「どうすれば、お年寄りが安全に暮らせるか」「災害時に役立つ情報システムは作れないか」など、社会とのつながりを意識した内容が増えてきます。



自分の作ったものが誰かの役に立つ喜びを感じられる、大切なステージというわけです。
【高校編】大学入試に出るって本当?「情報Ⅰ」で問われるのは考える力
高校では、2022年度から全員が必修科目「情報Ⅰ」を学び、大学入学共通テストの科目にもなりました。
「入試に出るなんて大変!」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。テストで問われるのは、専門的なプログラミング言語の知識そのものではありません。
大切なのは、問題解決のために、どういう手順で命令を組み立てればいいかという「論理的な思考力」。これは、高校までの授業でしっかり養われる力なので、過度に心配する必要はないのです。
【学年別】「わが家の対策」リアル体験ロードマップ


「学校でやることはわかったけど、家では何をすればいいの?」そんな疑問にお答えします。わが家(現在、子どもは小学3年生)のリアルな体験をもとに、おすすめの対策ロードマップを考えてみました。
- 低学年:遊びを通してPCに慣れることから
- 高学年:子どもの「好き」を深掘りし、創造へつなげる
- 中学生:将来を意識し、社会とのつながりを見つける
【小学1年生】まずは「楽しい!」から!PCゲームで遊びの世界を広げる
この時期に一番大切なのは、パソコンやタブレットに触れることへの抵抗感をなくし、「なんだか面白そう!」という気持ちを育てることです。
わが家では、世界的に人気のゲーム「マインクラフト」をきっかけに、パソコンに慣れていきました。最初はただ遊んでいるだけでしたが、次第に「もっとすごい建物を作りたい」と、自分で調べたり工夫したりするように。
この過程で、パソコンの操作に慣れ、キーボードやマウスが「楽しい道具」に変わっていきました。



難しいことをさせようとせず、とにかく「パソコンって面白い!」と感じさせることが、この時期のポイントですね。
【小学2年生】「もっとやりたい」を引き出す!Scratchで創造力をカタチに
ゲームに慣れてきた小学2年生のころ、次のステップとして「Scratch(スクラッチ)」を教えてみました。
| 項目 | マインクラフト | Scratch(スクラッチ) |
|---|---|---|
| できること | 用意された世界で遊ぶ | 自分で世界を作る |
| 役割 | 消費する側 | 創造する側 |
「このキャラクターを、こう動かしたいな」と考え、ブロックを組み合わせて、思い通りに動いたときの嬉しそうな顔は、今でも忘れられません。
- 得られた経験: 自分で考えて作ったゲームが動くという小さな成功体験
- 気持ちの変化: 子どもの「もっとやりたい!」という気持ちが大きく育ってくれました。
【小学3年生~高学年の計画】興味を「得意」に!教室も視野に入れ、本格的な挑戦へ
小学3年生になり、スクラッチにも慣れてくると、今度は「もっと複雑なゲームを作りたいけど、どうすればいいかわからない」という壁にぶつかりました。
そこで、プログラミング教室の体験に参加。同じ興味を持つ友達や、教えてくれる先生の存在が大きな刺激になったようで、今ではすっかりプログラミングに夢中です。
高学年に向けては、以下のような挑戦で「誰かに見てもらう喜び」や「社会とのつながり」を感じられる機会を作っていきたいと考えています。
- 友達との共同制作: 一人では作れないような、少し大きな作品作りに挑戦する。
- コンテストへの挑戦: 自分の作った作品を発表し、客観的な評価をもらう。
- Webサイトの作成: 自分の好きなこと(趣味や部活)を発信する簡単なサイト作りに取り組む。
【中学生以降の展望】将来の選択肢を意識。社会とのつながりを見つける
中学生になったら、さらに一歩進んで、より現実に近いテクノロジーに触れさせたいと思っています。
| 挑戦したいこと | 目的・ねらい |
|---|---|
| スマホアプリの分析 | 普段使っているアプリがどう作られているのか、その裏側を探る |
| Pythonなど言語の学習 | より本格的なプログラミング言語に触れ、作れるものの幅を広げる |
| 「情報Ⅰ」の先取り学習 | 高校の授業や、その先の進路選択を意識するきっかけ作り |
大切なのは、プログラミングが単なる「お勉強」ではなく、将来の自分の可能性を広げ、社会の問題を解決するための強力なツールなのだと気づかせてあげること。



高校の「情報Ⅰ」や、その先の進路選択にも、きっと良い影響を与えてくれるはずです。
【体験談】必修化に備えて、わが家で「やったこと」


いろいろな情報があると、「あれもこれもやらなきゃ」と焦ってしまいますよね。そこで、わが家が実際にどうしたか、リアルな体験談をお話しします。
- やったこと①:一緒に楽しむ時間を作った
- やったこと②:「なんで?」と考える会話を増やした
やったこと①:パソコンに触る「だけ」の時間を作った
わが家では、まず「パソコンは特別なものじゃない」という空気を作ることから始めました。
週末に15分だけ、保護者と一緒にパソコンに触る時間を作る。やったのは、お絵かきソフトで自由に絵を描いたり、好きな動物の画像を検索したり、本当にそれだけです。
大切なのは、「教える」のではなく「一緒に楽しむ」こと。マウスの操作やキーボードの配置も、そうやって遊んでいるうちに、子どもは勝手に覚えていきました。
やったこと②:「なんで?」を一緒に考える会話を増やした
もうひとつ意識したのは、日常会話の中で「なんでだろうね?」と問いかける回数を増やすこと。
「信号って、どうして順番に色が変わるんだろうね?」 「このゲーム、どうすればクリアできるかな?作戦会議しよう!」
こんな風に、物事の仕組みや手順を考えるきっかけを、意図的に作っていました。



これは、特別な道具がなくてもできる、とても効果的な「考える力」のトレーニングだったと感じています。
学校だけで足りる?プログラミング教室、通うべきか徹底比較
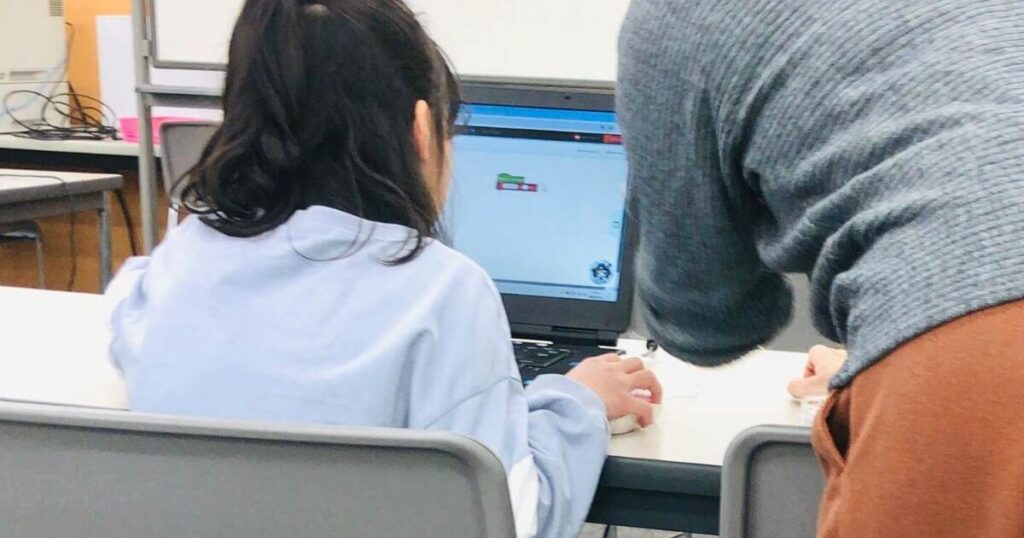
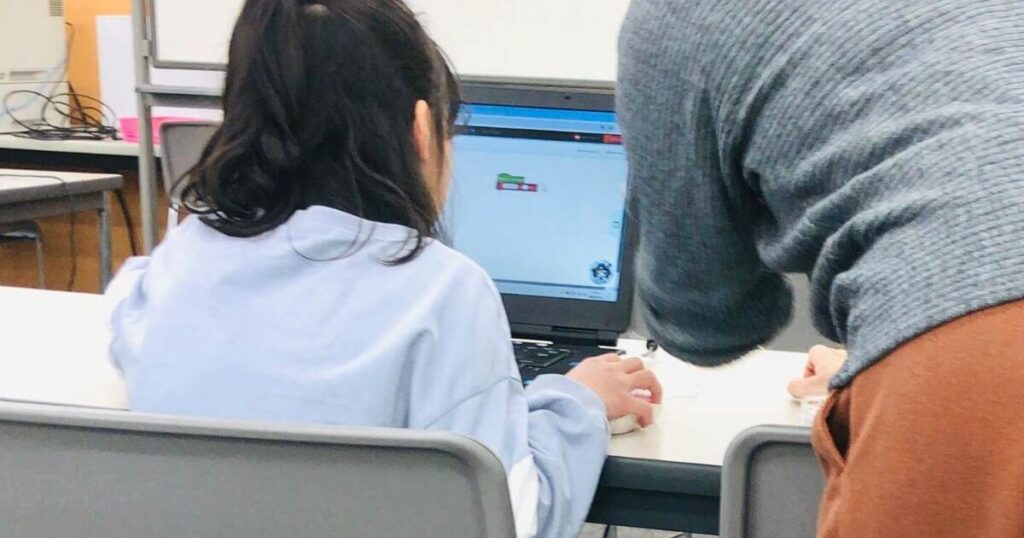
「学校の授業だけじゃ、やっぱり不安…」そんな時に選択肢になるのが、プログラミング教室。でも、本当に必要なのでしょうか?
- 教室は必須ではない
- 子どもの「もっとやりたい!」が判断基準
- まずは無料体験から始めるのがおすすめ
わが家の子はどっち?“もっとやりたい派”か“授業で満足派”かで見極める
まず大切なのは、「学校の授業についていく」のが目的なら、必ずしも教室は必要ないということ。
教室を検討するのは、その子自身が「もっとやりたい!」「もっと知りたい!」と強い興味を示したときで十分です。
| 判断基準 | 該当する例 |
|---|---|
| こんな子には教室が向いているかも | 学校の授業だけでは物足りなそう / 好きなゲームなどを自分で作りたがる / 専門の先生に質問しながら進めたい / 保護者と一緒に試行錯誤を楽しめる |
| まずは学校の授業で様子見でOK | 特にプログラミングに興味を示さない / 他の習い事で手一杯 |
お子さんの様子を見て、「授業だけでは物足りなそうだな」と感じたら、それは教室を考える良いタイミングかもしれません。
習い事っていくらかかる?教室の特徴と料金のリアル
教室に通うとなると、気になるのが料金ですよね。
- 月謝の相場
-
だいたい1万円~2万円ほど。
- 注意点
-
決して安くはないので、カリキュラムの内容や先生との相性などをしっかり見極めることが大切です。教室の形態(オンラインか通塾か)やコース内容によっても料金は変わってきます。


いきなり入会はもったいない!まずは“お試し体験”が失敗しないコツ
ほとんどの教室では、無料の体験授業を実施しています。
いきなり入会するのではなく、まずは親子で体験に参加してみるのが、失敗しない一番のコツです。
- 教室の雰囲気はどうか?
- 先生はどんな人か、子どもと合いそうか?
- そして何より、その子自身が「楽しい!」と感じられるか?
いくつかの教室を比較検討して、その子に合った場所を見つけてあげましょう。


まとめ|心配が「楽しみ」に変わる、はじめの一歩
この記事では、プログラミング必修化の本当のねらいから、各家庭に合った準備、そして具体的な授業内容までご紹介しました。
- プログラミング教育は、専門家を育てるのではなく、これからの時代に必要な「考える力」を育むための土台作りです。
- 大切なのは、保護者の方が先生になるのではなく、子どもの「楽しい!」という気持ちを応援し、試行錯誤できる時間を見守ってあげること。
- 学校の授業で基本は十分。周りと比べて焦る必要はありません。
- もし習い事を考えるなら、お子さんの「もっとやりたい!」という気持ちを一番の判断基準にしてみましょう。
「うちの子、ついていけるかな…」と心配する前に、まずは家庭でできる小さな一歩から始めてみませんか?
この記事が、必修化への不安を「わが子を応援する楽しみ」に変える、そのはじめの一歩となれば嬉しいです。